妊娠~出産後に行う15の手続きの一覧!
公開日:
:
最終更新日:2019/03/05
葉酸
妊娠が分かった時、赤ちゃんが産まれた時、ママとパパはやらなければならない手続きがいろいろ出てくるもの!面倒だな・・と思う方も多いかもしれませんが、大切な赤ちゃんを育てていくためには必要な事ですし、国や自治体などには手続きをするだけで受け取れるお金や助成金などの行政サービスがあり、これらの手続きをしないのははっきりいって損!
そこで今回は、妊娠から出産後のやらなければならない手続きを、わかりやすく一覧にまとめてみました。是非、参考にしてください!
もくじ
妊娠がわかった時の手続き!2つ!
病院で妊娠がはっきりと判明したら、行う手続きは次の2つです!
・妊娠届出書の提出⇒母子健康手帳の交付
・産休・育休の申請
妊娠届出書の提出⇒母子健康手帳の交付
妊娠が確定したら、最初にすることが「妊娠届出書」の提出です。この届け出をしてはじめて「母子健康手帳」が交付されますので、なるべく早く申請しましょう!
「母子健康手帳(母子手帳とも呼ばれる)」とは、妊娠中のママの経過や、出産後の赤ちゃんの健診、予防接種などの記録を記すことのできる大切な冊子です。
妊娠・育児の心得や注意なども載っており、妊娠がわかったら、まず手に入れたいのがこの母子健康手帳!自治体ごとに多少内容が異なるようですが、ほとんどの自治体で母子健康手帳の交付と同時に妊婦健診無料券などを一緒に配布している様です。
この母子健康手帳を手に入れるのに提出しなければならないのが、妊娠届出書になります。住民票のある自治体(多くは役所や保健センターなど)に提出するものですが、妊娠が判明した病院で発行してもらい、役所に提出する場合と役所などで用意された申請書に記入し提出する場合の2通りがあります。
手続きの方法は自治体によって異なるため、ご自分の自治体ではどのように手続きをするのか、調べておくことが大切ですね。
ちなみに私が住んでいる自治体では、届け出用紙を保健センターなどの申請場所で手に入れられる他、インターネットでダウンロードできるようにもなっています。このように、用紙がネットで手に入る自治体は多いようですよ。
産休・育休の申請
お仕事をしているママは、勤務先に「産前産後休暇(産休)」と「育児休業(育休)」の申請が必要になります。
産休は、出産予定日の6週間以内(双子以上の多胎妊娠は14週間以内)の期間、本人が希望すれば取れる「産前休暇」と、出産後8週間は休まなければならないと義務付けられている「産後休暇」の2つがあります。ただし、産後休暇の場合は、産後6週間を過ぎて、医師が復職に支障がないと認めた場合に限り、本人が希望すれば復職することができるとされています。
一方、育休は、育児・介護休業法で定められているお休みのことで、勤続1年以上であれば子どもが1歳になるまで休業することができるというもの。休業したい日の1ヶ月前までに会社に申請することになっていますが、復職することがこの育休の条件となります。
いずれにしても、産休や育休を合計3年取ることができるなど、会社ごとに独自の産休・育休期間を定めているところが多いようです!手続き方法なども含めて、まずは勤務先に問い合わせることが大切です。また、今は、ママだけでなくパパも育休が取れる会社も増えていますよね!
妊娠や出産で退職する時の手続き!
妊娠や出産をきっかけに会社を退職する方もいますよね。そんな時に必要なのが、こちらの手続きです。妊娠・出産後の特別措置が受けられます。
・失業給付金⇒受給期間の延長申請
失業給付金⇒受給期間の延長申請
失業給付金は、退職前に6ヶ月以上雇用保険に加入していた方が対象となるもので、1ヶ月分の給与の6割が支給されます。
また、妊娠・出産後のママは特別措置として、一般に1年間しかもらえない失業給付金を延長申請をすれば、最長4年まで延ばすことができます。
申請期間は、失業給付金の場合、退職日の翌日~1ヶ月以内。受給期間延長の申請の場合は、退職翌日から30日目経過した翌日~1ヶ月以内となっています。
申請場所は、ハローワークで、離職票・雇用保険被保険者証・申請者本人を確認できるもの・母子手帳・印鑑などが必要になります。
12もある!出産後の手続き!
いよいよ赤ちゃんを出産!出生届をはじめとして、手続きの方もしなければならないものが山積みです!対象になっている方は、抜けがないようにしっかりと手続きをしていきましょう!
・出産育児一時金・出産育児付加金の申請
・出生届の提出
・出生通知表の送付
・未熟児養育医療給付金の申請
・健康保険加入の申請
・乳幼児の医療費助成の申請
・児童手当の申請
・出産手当金の申請
・育児休業給付金の申請
・医療費控除の申請
・高額医療費の申請
・医療保険の申請
出産育児一時金・出産育児付加金の申請
「出産育児一時金」は、健康保険か国民健康保険に加入していて、妊娠4カ月以上で出産したときに受け取れるお金のことで、原則、子ども1人につき42万円、多胎の場合は人数分を受給できるというもの。
また、この出産育児一時金には、一時金の請求と受取りを妊婦に代わって医療機関が行い、出産費用が医療機関に直接支払われる「直接支払制度」と、妊婦が出産予定日の2ヶ月前に健保組合に手続きをして、健保から医療機関へ費用が直接支払われる「受取代理制度」の2種類があります。
直接支払制度の場合は、申請なども医療機関が全てやってくれるので、出産時の入院中に必要書類に記入するだけと簡単!
退院時は42万円を超えた差額を病院側へ支払うだけで済み、反対に、出産費用が42万円よりも安く済んだ場合は、手続きをすれば1~2ヶ月後に残りの金額が指定口座に支給されます。
現在、ほとんどの病院で「直接支払制度」が採用されているのですが、小規模な産院などでは利用できないこともあるのだとか。念のためにご自分がかかっている病院で利用できるかどうか尋ねておきましょう。
一方、「出産育児付加金」とは、それぞれの健康保険組合が独自に給付しているお金のこと。出産育児一時金に追加して給付されるのですが、加入している組合によって金額や有無なども異なるため、ご自分が加入している健保組合に問い合わせる必要があります。
出生届の提出
「出生届」は、赤ちゃんを戸籍に登録するための手続きで、赤ちゃんが産まれたら、出産日を含めて14日以内(国外での出産は3ヶ月以内)に、住民票のある地域か本籍地の市区町村役所、もしくは赤ちゃんが生まれた地域の役場などで出すことができます。
届け出に必要なものは、母子手帳・出生届・健康保険証・申請者本人を確認できるもの・印鑑です。申請者は原則、両親のいずれかですが、代理人でも可能だとか。
また出生届は、出産した病院で貰えることがほとんどです。用紙には、病院に記入してもらう出生証明書の欄がありますので、忘れずに記入してもらいましょう。病院が出生届を用意していない場合は、役所で貰えますので、退院までに用意して記入してもう必要がありますね。
また、出生届にはもちろん赤ちゃんの名前が必要になります!
どんな名前にするか考えるのもパパ・ママになった実感を深めてくれますね!
出生通知表の送付
「出生通知表」とは、母子健康手帳といっしょに渡される、文字通り赤ちゃんが産まれたことを通知するハガキのこと。
赤ちゃんが産まれたら14日以内にお住いの市区町村の保健センター宛に送付すると、保健婦が赤ちゃんやママの様子を見に来てくれ、相談などにのってくれる「赤ちゃん訪問相談」や、保健所が行っている乳幼児健康診査、予防接種のお知らせなどが届くようになっているのだとか。
また、この通知表は、「低体重児届出兼用」になっており、母子保健法により、2500g未満の低出生体重児を出産された方は、低体重児の届出をすることが義務づけられています。忘れずに送付するようにしましょう!
未熟児養育医療給付金の申請
出産時、産まれた赤ちゃんが未熟児の場合、もしくは医師から入院養育が必要と判断された場合、入院や治療費を自治体が援助してくれる制度が、「未熟児養育医療給付金」制度です。
これには、出産日から14日以内に保健センターなどでの申請が必要で、必要書類は各自治体で異なっていますので、必要な方は問い合わせてみるのが確実です。
基本、未熟児養育医療給付申請書・未熟児養育医療意見書・世帯調書・母子健康手帳・源泉徴収票などの所得税証明書・乳幼児医療費受給者証・健康保険証・印鑑などが必要になるそうです。
健康保険加入の申請
産まれた赤ちゃんを健康保険に加入させる場合、パパ・ママの両方が働いているのならどちらでもいいのですが、一般的には年間収入の高い方の扶養に入れることが多いようです。
必要なものは、出生届出済証明が記入された母子健康手帳・出生届のコピー・申請者(パパかママ)の健康保険証・印鑑。
1ヶ月検診に間に合うように、勤務先の健康保険組合か、国民健康保険の場合は住民票のある市区町村役所へ申請書類を提出するようにしましょう。
乳幼児の医療費助成の申請
赤ちゃんが健康保険に加入できたら、同じく1ヶ月検診までに済ませたい手続きが、「乳幼児の医療費助成」の申請です。
これは、赤ちゃんの医療費を助成して貰える制度で、自治体によって制度の内容が異なるのですが、申請後に交付される「乳幼児医療証」を病院の窓口で見せると、赤ちゃんの医療費が無料や定額になったりするもの。
自治体ごとに、所得制限や助成が受けられる年齢や方法が異なったりするので、細かな内容については確認が必要です。
申請は、住民票のある自治体の役所で行い、必要なものは、母子健康手帳・赤ちゃんの健康保険証・普通預金通帳・印鑑などです。
児童手当の申請
「児童手当」とは、子どもの育児を支援する目的として、国と地方自治体から支給されるお金のこと。給付期間は、現在のところ、中学校を卒業するまでの間とされていますね。
支給される金額は子供の年齢によって変わり、
0~3歳未満まで:一人につき月額1万5千円
3歳~小学校修了まで:第1子・第2子が月額1万円・第3子~1万5千円
中学生:月額1万円
となっています。ただし、扶養人数や所得制限の枠があるため、給付金額は人によって変わることがあります。また、当分の間は特例給付として、所得制限以上でも月額5千円が支給されるようになっています。
申請は、公務員の方は勤務先で、それ以外の方は住民票のある市区町村の役所で行います。申請の期限は、特にないようですが、申請した月の翌月分から支給となりますので、早目に手続きをする方がお得です!
届出に必要なものは、届出人の印鑑・パパやママなどの請求者の健康保険証・請求者名義の普通預金通帳・所得証明書など。その年に転居した場合は、所得証明書の代わりに課税証明書が必要になるようです。
支払いは銀行振込で、毎年2月・6月・10月に前月までの分がまとめて支払われます。
出産手当金の申請
こちらは、会社で健康保険に加入し、働いているママが対象になります。赤ちゃんが産まれると産休に入りますが、その間は給料が発生しないため、健康保険から給料の2/3が手当金として支給されるのです。
給付期間は、産前42日間・産後56日間で、申請の期限は産休開始翌日~56日以内となります。申請は勤務先で、出産手当金申請書・印鑑・健康保険証・振込先口座・出生を証明する書類などが必要です。
また、同じく勤務先に申請すると貰えるかもしれないのが、「出産祝い金」。
各会社ごとにルールや有無なども異なるようですが、出産手当金などの申請の際に確認してみるのもいいでしょう。
育児休業給付金の申請
「育児休業給付金」は働いているママ、正確に言うと育児休業前に2年以上働いていて、雇用保険に入っているママが対象になるもので、育児休暇中、給与の1/2が雇用保険から支給される制度のこと。
申請の期限は、育休開始日の1ヶ月前まで。勤務先に申請します。
必要なものは、出生を証明する書類・育児休業給付金の申請書・印鑑・振込先口座。
また、育休中に保育園が決まらないなど、職場復帰が難しい事情がある時は、育休を最大半年まで延長することができ、給付金も延長して受給することができます。
ただし、その際には、役所から発行される「不承諾通知書」をもって延長申請をする必要があるそうです。
医療費控除の申請
「医療費控除」とは、家族全員で1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の合計が出産費用も含めて10万円以上かかった場合、確定申告を行うことで払いすぎた税金が戻ってくる制度のこと。
ただし、出産育児一時金の42万円は総額から差し引かれますので、対象になる方はそう多くはないと思われます。医療費の他にも通院するための交通費や薬局で購入した薬代なども控除の対象になります。この医療控除は出産した年だけでなく、毎年行うことができますので、念のためにレシートや領収書は毎年、1年間分を取っておくようにしましょう。
申請の期限は、申告したい年の翌年3月の確定申告で、5年以内ならさかのぼって請求することができます。必要なものは、確定申告書・医療費の明細書・出産にかかわる費用の領収書など。還付が決まれば、銀行口座も必要になるかもしれません。
高額医療費の申請
「高額医療費」とは、健康保険が適用される治療を受け、1ヶ月間に自己負担限度額を超える医療費がかかった場合、その超過分を健康保険から返還してくれる制度のこと。
妊娠や出産で、切迫早産、入院、帝王切開、陣痛促進剤の使用などの治療を受け、高額な医療費がかかった際にも適用されます。
申請先は、加入している健康保険組合。国民健康保険の場合は、住民票のある市区町村役所になります。申請可能な期間は、診察日の翌月~2年以内となっており、届出人の印鑑・健康保険証・医療費の領収証・高額医療費支給の申請書などが必要になります。
また、自己負担限度額は健康保険組合によっても異なりますので、高額な医療費がかかった場合はご自分の加入している健康保険組合の定める限度額がいくらなのか、一度確認してみましょう。
医療保険の申請
妊娠中や出産前に病気で入院したり、出産時に帝王切開などの手術を受けたりした場合、民間の医療保険に加入していれば、入院給付金や手術給付金受け取りの対象になることがあります。
もちろん加入している保険によって対象となる治療は異なりますが、もしかしたら対象になるかも・・?という方は、契約書か保険会社へ問い合わせて、確認するのを忘れずに!もし対象となるのなら、必要書類を取り寄せ、記入して保険会社へ提出すればOKです。
関連記事
-
-
夫婦で旦那も妊活!男性にも葉酸サプリが必要な理由
葉酸は妊娠、授乳期において母子の健康に重要な栄養素です。そのため、女性が摂取するイメージが強
-
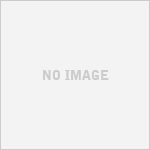
-
【不要?】学資保険は必要と私が考える4つの理由!
子育て世代に人気の学資保険!しかし、学資保険は必要ない!という意見も、ちまたではよく聞かれます。
-
-
ほうれん草の葉酸含有量はどのくらい?妊娠中の調理法やレシピを公開
葉酸は、妊娠初期に形成される赤ちゃんの神経管閉鎖障害の発症を予防する効果があります。そのため
-
-
妊娠中の寒気の原因と対策!流産や腹痛から学ぶ寒気の症状
妊娠してから「ゾクゾクするような寒気をよく感じる」「風邪でもないのに何だか寒い……」という経
-
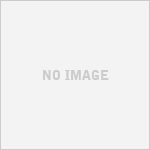
-
学資保険は妊娠中で出産前でも加入できる!メリットは?
学資保険というと、子どもの将来の教育費の備えとして子育て世代に大変人気がありますが、実は赤ちゃんが産
-
-
葉酸タブレットと葉酸サプリメントの効果やおすすめ度を検証する
葉酸には、赤ちゃんの神経管閉鎖障害を防ぐ効果があります。このとき水や熱に弱い葉酸を効率よく体
-
-
妊娠中の食欲増加の理由とは?3つの対策法を紹介!
妊娠中は、たくさん食べているのに常に「お腹が空いている」と感じたり、糖分をたっぷり含んだ甘い
-
-
出産の立ち会い!夫がするべき準備とは?
「立ち会い出産」。今ではすっかり世間に定着し、実際に我が子の出産に立ち会ったというパパも少なくない時
-
-
妊婦が運動を始められるのはいつから?そしていつまで大丈夫?
マタニティヨガ、マタニティスイミングなどの言葉が広く知られるようになり、妊婦さんでも運動を楽しんだり
-
-
妊娠の安定期の期間はいつからいつまで?注意点は?
妊娠の安定期というと、赤ちゃんが安定して流産の心配も低下し、辛いつわりがおさまってくる時期と言われて










